 |
大型陶器の画家
アンドキデスの画家によって発明され、エウフロニオスら開拓者たちによってその可能性が花開き始めた赤像式は、この時代になってその頂点に達したといえる。その頂点となる作品を残したのがクレオフラデスの画家(Kleophrades
Painter)とベルリンの画家(Berlin Painter)である。彼らはエウフロニオスよりもエウテュミデスやフィンティアスの影響が強く、特にクレオフラデスの画家には開拓者的な様式や雰囲気が残る。彼の像は力強く重みがあるのにたいし、ベルリンの画家の像は軽く、より優雅に描かれている。
クレオフラデスの画家は、彼の陶器にエピクテトスというサインが見られ、「エピクテトス2」と呼ばれることもあったが、このサインは後世、おそらくは現代になってつけ加えられたものであろうという議論が起こり、結局この名称が用いられている[1]。その名前の由来となっている陶工クレオフラデスは自らのサインに父親の名前をつけ加えており、その父親アマシスはおそらく黒像式の時代に活躍した人物であろうと考えられている。
この画家の活動は505-475年頃で、その初期の作品は特にエウテュミデスに近く、ミュンヘン古代美術館所蔵の尖底アンフォラ(図1,munich2344)もその一例である。頚部には五種競技の場面が、胴部にはディオニュソスを中心にサテュロスとマイナスが描かれている。ここでは黒を薄めた茶色による描写が多用されている。また画面を支える装飾帯は複雑なメアンダー文で、このほかにもT字型によって構成されるメアンダー文などもあり、彼の特徴のひとつとなっている。
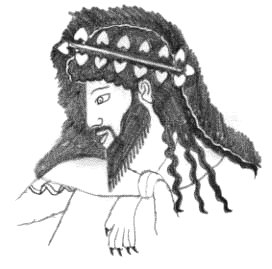
図1
彼の傑作といえるのがナポリ国立考古博物館所蔵のカルピス式ヒュドリア(naples2422)である[2]。ここに描かれているのはトロイア陥落の場面であるが、これまでに見られない構成が用いられている。カルピス式はすでに開拓者の時代に用いられていたが、いずれも正面部分のみに画面を設けるものであり、このようにほぼ全周にわたる画面はこれまでにないものであった。特にこの画面構成はカップ外面とは正反対の、画面上部に比べ下が広がるもので、これに適応するように倒れたり、しゃがんだりする像が描かれている。
それぞれの人物も、すでに殺された孫アステュアナクスを膝に乗せ、自らもネオプトレモスに殺されようとするトロイア王プリアモスを始め、展開するおぞましい光景に頭を抱える女性や、果敢にギリシア兵士に抵抗する女性、かすかな希望を求めて脱出するアイネイアス一家、祖母アイトラを救出するアカマスとデモフォンなど、様々な立場、心理を持つ人物たちが描き分けられている。
古代地中海美術館所蔵のコラムクラテルもこの大家による作品である。ここに描かれているのはヘラクレスがケンタウロス族のフォロスのもとを訪れ、一族共有の甕を無理矢理開けてしまい、その後両者の闘いへ展開する場面である。この主題はこの画家の好んだもののひとつであり、描写は彼の中では平凡なものだが、日本にある赤像式陶器の中でも傑作のひとつであろう。
ベルリンの画家はクレオフラデスの画家にやや遅れ、500-460年頃に活動したが、作品の多くはその前半に属するものである[3]。彼もまた開拓者たちと同様に神話の劇的な場面を取り上げているが、それとは別に、彼の最大の特徴となっているのは、アンフォラやクラテルなど大型陶器の画面に対してわずかに一人か二人の人物しか描かない構成であり、装飾はいっさい省かれて人物以外はすべて黒で塗りつぶされ、それ以外では時に人物の立つ地平面としてメアンダー文などが描かれるのみである。
そしてその人物もまるで肖像画のように静かな動きによって描かれている。彼の名前の由来となっているベルリン古代美術館所蔵のベリィアンフォラ(図2,berlin2160)は、こうした例には珍しく頚部に装飾が見られるものだが、ヘルメスと鹿とともに描かれているサテュロスは、これまでのアッティカ陶器に見られた粗野で好色な姿ではなく、物静かな、神にも等しい気品を備えた姿で描かれている。
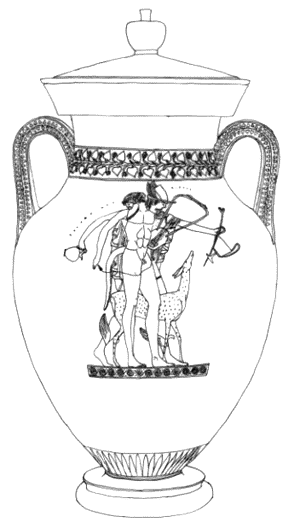
図2
彼の傑作のひとつがバーゼル古代博物館所蔵のベリィアンフォラである。主題はヘラクレスと、常に彼を守護した女神アテナであるが、一切余計なものは省かれ、一面にヘラクレスを、他面にアテナを描いている。特にアテナの描写は優れていて、その描写の手法は異なるながらもその精確さはエクセキアスに通じるものであり、エクセキアスによって黒像式が頂点に達したように、ベルリンの画家によって赤像式もひとつの頂点に達したということができよう。しかし黒像式がその後急速に品質を低下させたのとは異なり、赤像式はこれほどの作品は見られなくなるもののやはり優れた作品は作られ続けた。
なおこのベルリンの画家について、六世紀末にキュリクスを中心に描いたゴルゴスという名の画家の作品はこの画家の初期のものであるという説が出され、ビーズレイもこれを一部認めているが、これに対する反対意見もあり、現在でも未解決のままである[4]。
この二人をのぞく重要な画家としては、まずミュソン(Myson)があげられよう[5]。彼の傑作といえるのがルーヴル美術館所蔵のベリィアンフォラであり、アッティカ式陶器の中でも特異な例といえる。ここで積み上げられた薪の上に乗せられているのは小アジアのリュディアのクロイソス王であり、ヘロドトスによって語られている場面を描いたものである。このような歴史上の人物が描かれる例はきわめてまれであり、彼が半ば神話上の人物として扱われていたことがわかる。京都ギリシア・ローマ美術館所蔵のコラムクラテルもこの画家によるもので、ベルリンの画家のように画面に一人の人物のみを描いている。
このほかでは、ボストン美術館所蔵のカリュクスクラテルなど神話の場面を好んだティッシュキーエヴィッチの画家(Tyszkiewicz
Painter)の他、メトロポリタン美術館所蔵のカルピス式ヒュドリアなど、ベルリンの画家のようなシンプルな構成を好んだトロイロスの画家(Troilos
Painter)、古典時代に流行する陶器の画面を上下二段に分割した構成をもつ尖底アンフォラを描いたシュレウスの画家(Syleus
Painter)、黒像式も描いたニコクセノスの画家(Nikoxenos
Painter)とその後継者のエウカリデスの画家(Eucharides
Painter)などがあげられる[6]。いずれもクレオフラデスの画家やベルリンの画家には劣るもののそれぞれ特徴を持ち、優れた画家であることは確かである。
小型陶器の画家
大型陶器において二人の大家が生まれたように、小型陶器においても三人の大家が活躍した。しかしこの三人について述べる前に、彼らよりもわずかに年長の画家について述べる必要がある。
まずはじめにあげられるのがペイティノス(Peithinos)である。ベルリン古代美術館所蔵のキュリクスを見ると、衣服の褶はかなり細かく描写され、裾の部分も丁寧に描かれており、その描写はソシアスの画家に近いが、目の描写はよりアルカイック的である。彼の作品は少なく、ほとんどが断片的なものである。
ついで優れた作品を数多く残しているのがオネシモス(Onesimos)である[7]。なお彼の初期の作品はパナイティオスの画家(Panaitios Painter)として分類されていたが、現在では両者は同一人物と見なされている。彼の傑作といえるのがルーヴル美術館所蔵のキュリクスである。ここでは内面のトンドをかなり大きくとり、テセウスがアテナとともに海中のポセイドンとアムフィトリテの宮殿を訪れた場面を描いている。テセウスの足下を支えるトリトンや画面左を泳ぐイルカなどによってここが海中であることが示されている。衣服の褶を始め、髪の表現やアテナのアイギスなど、かなり丁寧な描写が見られる。外面はスキロンなどを退治するテセウスが描かれている。
彼はこのような神話を主題としたものも描いてはいるが、もっとも好んだのは女性の生活や宴の場面などの描写である。大英博物館所蔵のキュリクスもそうした例のひとつであり、特に右側の人物は頭ははげて鼻にはこぶがあり、これまでの理想化された人物像だけでなく、このような個人的な特徴を描く例がしばしば見られるようになった。このほかにはケンタウロス族や戦いの場面ばかりを好んだボンの画家、風俗画を専門にしたコルマーの画家(Colmar
Painter)、多作でやはり風俗画を好んだアンティフォンの画家(Antiphon
Painter)などがいるが、いずれもその描写は二流であった。
ここから三人の大家について扱うが、彼らの関係は三大悲劇詩人になぞらえることができるかもしれない。つまりやや先輩にあたるブリュゴスの画家は力強いアイスキュロスの作風、ドゥーリスは優雅なソフォクレス、マクロンは円熟に達する一方形式化も覗かせるエウリピデスの作風を連想させる。ブリュゴスの画家(Brygos
Painter)はその名前は陶工ブリュゴスのサインのある陶器に描くことが多いことから名付けられた[8]。その描写は特に精確というわけではないけれども、その主題の選択や構成、像の姿勢などはかなり独創的であり、描写の欠点を補うにあまりあるほどである。彼の描く人物は特徴があり、目は細くて眉毛との間に距離があり、鼻は大きめである。彼の作品の中でも印象的なのが、内面トンドに白地を用いたミュンヘン古代美術館所蔵のキュリクスである。舞い踊るマイナスの姿は軽やかで、これも背景に黒ではなく白地を用いているためであろう。この頃からキュリクスの内面に白地を用いる例が時折見られるようになり、そのほとんどが優れた描写を持つ。
彼の傑作のひとつがルーヴル美術館所蔵のキュリクスである。その主題は内外面ともトロイア戦争を題材にしたものであるが、内面のフォイニクスとブリセイスと解されている人物の穏やかな場面に比べ、外面はクレオフラデスの画家も描いたトロイア陥落の劇的な場面である。斬新さという点ではクレオフラデスの画家に軍配が上がるが、その迫力は十分に伝わってくる。これらキュリクス以外にも彼はスキャフォスやリュトン、さらには特異なカラトスと呼ばれる底部に口の付いた陶器にも描いている。
彼に続くのがドゥーリス(Douris)である[9]。彼は非常に優れた画家であり、その描写は美しい。しかしブリュゴスの画家ほどの個性はなく、特徴といえばやや丸い感じの頭部とかぎ型に描かれた鎖骨、引き締まった唇、細いプロポーションなどである。彼の活動は500年頃から460年近くにまで及び、その作品も300以上が確認されている。彼の活動期はしばしばその描写や好んだ画題などから四つの期間に分割される。概して描写は後期のものより前期のものが優れていて、初期と末期には装飾を細かに描く傾向がある。
その画題も多岐に渡り、特に初期の好まれた饗宴の場面、前期に好まれた陸上競技の場面などの風俗画のほか神話の場面も数多く描いているが、中にはヴァチカン博物館所蔵のキュリクスに描かれた、イアソンが竜の口から吐き出される場面などのように文学作品には伝わらない場面が描かれていて興味深い。彼はキュリクスのほかにもプシュクテルやカンタロス、アリュバロスなどにも描いていて、クリーヴランド美術館所蔵のレキュトス(cleveland66.114)は白地の上に女傑アタランテとエロスが美しく描かれている。
大家の三人目マクロン(Makron)は陶工ヒエロン(Hieron)とともに活動した[10]。彼はこの時代で最も多作な画家であり、350点以上が彼に同定されている。その描写はほかの二人に比べてやや雑なものが多く、彼の描く人物の頭部は大きくて頭頂部が扁平であるという特徴を持つ。しかし中には丁寧に描かれた人物もあり、衣服に多彩な装飾が施される。特に優れた描写が見られるのはカップよりもスキュフォスで、大英博物館所蔵のスキュフォス(londonE140)には翼の生えた車で麦の栽培を伝えるトリプトレモスが描かれているが、彼の隣に立つデメテルの衣服にはイルカや翼の生えた人物、鳥、戦車などが細かく描かれている。
彼の描く画題は多様だが、神話の場面に限ればトロイア戦争を題材としたものが多いのが特徴である。彼はキュリクスのほかにも先に述べたスキュフォス、アリュバロス、アスコスなどにも描いている。
これら三人のほかにも作品の数は少ないものの彼らに劣らない描写を見せる画家も存在した。鋳造工房の画家(Foundry
Painter)はブリュゴスの画家に近く、その技術も劣るものではないが像自体の力強さに欠ける。ブリュゴスの画家の後継者で、キュリクスのほかにもクラテルなど大型陶器に描くことを好んだブリセイスの画家(Briseis
Painter)やドキマシアの画家(Dokimasia Painter)もやはり活力と個性に欠ける。ドゥーリスの影響を受けた画家にはオイディプスの画家(Oidipous
Painter)とトリプトレモスの画家(Triptolemos
Painter)がいるが、前者がドゥーリスの後期に見られる劣った描写とのつながりが深いのに対し、後者はその影響を受けながらも独自の特徴を持ち、特に大型陶器には優れた描写が見られる。
| [1] |
クレオフラデスの画家については、Beazley,
J. D., The Kleophrades painter,
(1974), Beazley, J. D., "Kleophrades",
JHS 30, pp.38-68, Richter,
G. M. A., "The Kleophrades
Painter", AJA 40,
pp.100-115参照。エピクテトスのサインの議論については、Boardman,
J. and U. Gehrig, "Epiktetos
II R.I.P., AA 1981, pp.329-332参照。 |
| [2] |
ナポリのヒュドリアについては、Boardman,
J., "The Kleophrades Painter
at Troy", AK 19,
pp.3-18参照。 |
| [3] |
ベルリンの画家については、Beazley,
J. D., The Berlin painter,
(1974), Curtz, D. C. , The
Berlin painter, (1983),
Beazley, J. D., "The Master
of the Berlin amphora",
JHS 31, pp.276-295, Beazley,
J. D., "Citharoedus",
JHS 42, pp.70-98参照。 |
| [4] |
ベルリンの画家の初期の作品についての議論は、Robertson,
M., "Origins of the Berlin
Painter", JHS 70,
pp.23-34, Robertson, M., "The
Gorgos cup", AJA
62, pp.55-66, Cardon, C. M.,
"The Gorgos cup",
AJA 83, pp.169-173, Pinney,
G. F., "The nonage of the
Berlin Painter", AJA
85, pp.145-158, Kurtz, D., "Gorgos'
cup:an essay in connoisseurship",
JHS 103, pp.68-86参照。 |
| [5] |
ミュソンについては、Berge,
L., Myson: a Craftsman of
Athenian Red-figured Vases,
(1992)参照。 |
| [6] |
ティッシュキーエヴィッチの画家については、Beazley,
J. D., "Fragment of a vase
in Oxford and the Painter of
the Tyszkiewicz crater in Boston",
AJA 20, pp.144-153参照。トロイロスの画家については、Beazley,
J. D., "The Master of the
Troilus-Hydria in the British
Museum", JHS 32,
pp.171-173参照。ニコクセノスの画家については、Beazley,
J. D., "The Master of the
Stroganoff Nikoxenos vase",
BSA 19, pp.229-247参照。Beazley,
J. D., "The Master of the
Eucharides-stamnos in Copenhagen",
BSA 18, pp.217-233参照。 |
| [7] |
オネシモスについては、Sparkes,
B. A., "Aspects of Onesimos",
in; Boulter, C. G. (ed.),
Greek art: Archaic into Classical,
pp.18-39, (1985), Maffre, J.
J., RA 1972, pp.221-参照。 |
| [8] |
ブリュゴスの画家については、Cambitoglou,
A., The Brygos painter,
(1968), Wegner, M., Der Brygosmaler,
(1973)参照。 |
| [9] |
ドゥーリスについては、Buitron-Oliver,
D., Douris: a master-painter
of Athenian red-figure vases,
Kerameus 9, (1995), Pottier,
E., Douris And The Painters
Of Greek Vases, (1908)参照。 |
| [10] |
マクロンについては、Kunisch,
N., Makron, (1997)参照。 |
|
 |