60年代のイベント
ミスター・ジャイアンツ〜長島茂雄
神宮の森に“スーパーヒーロー”誕生
私が物心ついて、自分で積極的に新聞の野球記事を見たりするようになった頃、新鮮な私の脳ミソにプリンティングされたセ・リーグのAクラスチームというのは、巨人と阪神と大洋の3球団であり、親父が給料から支援費用を天引きされていた国鉄スワロースと中日、広島の3球団はBクラスのイメージでした。セ・リーグでいうと、大洋が初優勝したのが1960(昭和35)年のことでありまして、翌1961(昭和36)年は巨人、翌々1962(昭和37)年は阪神というような状況だったわけです。
私は、小学校3年の頃だったと思いますが、東芝から発売されていた「輝くジャイアンツ」という小冊子に3枚のソノシートがついているものを、長岡市内のデパートの古本市みたいなところで買いました。このソノシートは小学校の間、繰り返し、繰り返し、何度も聴いたものです。越智正典さんのナレーションで、「戦後のプロ野球は焦土の中から雄々しく立ち上がった」という語りから始まるもので、1961(昭和36)年の巨人vs南海による日本シリーズ第4戦で、9回裏まで2−1でリードしていた南海のピッチャー・スタンカが、最後のバッターになるはずだった宮本に投じた2ストライクからのきわどい投球をボールと判定されて激怒し、実況のアナウンサーが「スタンカ怒った、スタンカ怒った、園城寺球審に歩み寄りました」と絶叫する声は、今も、私の耳にしっかりと残っています。ですから、恐らく、この「輝くジャイアンツ」というソノシートは、最終的に4勝2敗で巨人が南海を下して日本シリーズを制した1961(昭和36)年の翌年の1962(昭和37)年に発売されたものと思われます。
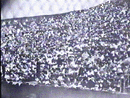 |
 |
前置きが長くなりましたが、その「輝くジャイアンツ」に付いていた3枚のソノシートのうち、1枚目の最後に録音されていたのが、長島茂雄による東京六大学野球新記録となる8本目のホームランの場面で、この実況も、私は、暗記するほど、聞き込んだものでした。 この実況は、結構、淡白で、カーンという打球音に続いて、「長島打った、レフトへ打球が伸びる、大きい、あ、入った、入った、ホームランです。長島、第8号のホームラン。連盟新記録のホームランです。長島、踊りながら、3塁を回って、コーチと抱き合いながら、今、チームメートに迎えられて、ホームイン。長島くん、おめでとう」というようなものでした。さらに、この後、「見〜よ、見〜よ、立っ教〜、自由の学府」という立教応援団のダミ声の効果をバックに、「あれは、確か、林君の失投じゃないですかねぇ」とインタビューに答える長島の声も入っていました。すでに、この頃から、論理的な文脈のつながりというものを一切無視する、長島一流の感性による言葉の展開の兆しも見え始めているわけであります。
話の流れとしては、前後してしまいますが、この六大学野球連盟新記録となった長島の8本目のホームランは、1957(昭和32)年11月3日、東京・神宮球場で行われた長島にとって六大学最後の試合である対慶応戦の5回裏、慶応の林投手から放ったものでした。
改めて、当時の映像をじっくりと見てみますと、まず、気がつくのは、当時の六大学では、選手のユニフォームの背中に背番号がついていませんし、長島がかぶっているのもヘルメットではなく、普通の野球帽であります。当時、まだ、ヘルメットがなかったとは思えませんので、今のように、打席に入る時には、必ず、ヘルメットを着用しなければならない、というような規定はなかったのだろうと思われます。
当時、ソノシートの実況を聴いていた私は、アナウンサーの「踊りながら」という表現を怪訝に思ったものでしたが、今、当時の映像を見ると、その表現は極めて正確な表現でありまして、長島は確かに、2塁ベースを回る辺りから「踊る」としか表現しえないような走り方を始めておりまして、3塁ベースを回るときには、ほとんど3塁コーチとダンスを踊っているのではないかと思われるような感じで、抱き合いながらホームインしています。すでに、学生時代から、こうした華やかなパフォーマンスというものが自然に出来てしまう人だったということなのでしょう。
また、このソノシートでは、当時の立教大学野球部の砂押監督によるスパルタの練習なども紹介されていたのを覚えています。後年、長島が引退したときに、ワーナーパイオニアから出た長島茂雄物語のような2枚組のLPも購入しましたが、こちらでは、あの芥川比呂志の味わい深い語りで、照明もなかったグランドで薄暗くなってからもノックが続き、「ボールが見えない」という選手の訴えに対して「心の目で見ろ。心の目でっ」と叱りつけたというメチャクチャなエピソードも紹介されておりました。
その立教時代の長島と砂押監督の関係については、五味康祐の著になる『小説・長島茂雄』(光文社カッパノベルズ)に詳しく書かれておりますので、紹介させていただきます。
 |
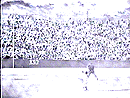 |
 |
 |
「立教へ入る前−−昭和28年冬−−長島は伊東球場で行われる立大野球部の冬季合宿に加わった。これは翌春卒業予定の高校生の合同セレクションで、いわば誰を立大に入れるかのふるいにかけるのである。長島が杉浦(挙母高)、本屋敷(芦屋高)と初めて顔を合わせたのもこの合同セレクションでだった。砂押監督は書いている−−−
『冬季練習に参加した高校選手の中で最も注目されていたのは甲子園出場の経験を持つ本屋敷である。彼はほとんど完全といっていいほど洗練された選手、一分のスキもない華麗なプレーで、本屋敷に比べると長島や杉浦はあまりにも未完成だった。二人とも県下の大会では相当鳴らしたようだが、甲子園組とはないようがちがう。練習のコツとか、試合の駈け引きなどはまるでゼロ。技術はあってもその出し方がわからぬ感じだった。
だが、私はこの“未完の部分”に魅力を感じた。変なクセが身についておらず、すべてに素直で、バッティング一つをとっても強引に引っ張るようなことはせず、センター中心に打ち返す基本に忠実な打法で、いわゆる鍛え甲斐のある選手と見込んだのである。
翌春、正式に立大入学が決まり、彼とのたたかいがはじまった。まず、基礎体力づくりにポイントをしぼった。当時の長島はバッティングはともかく、守備に関しては本屋敷とくらべたらそれこそ月とスッポンで、それもこれも、下半身の鍛練不足が原因と思えたのである。
とにかく走らせた。守備に重点をおき、猛ノックを連日続けた。後にマスコミは“千本ノック”とオーバーな表現を使ったが、千本はともかく、数え切れぬほど矢つぎ早やに浴びせたのは確かで、時には、真っ暗になるまでノックしたこともある。
東長崎の立大のグランド。
日が落ちてどのくらい経ったか、打球が飛ぶごとに確実に闇は深くなっていった。それで石灰をまぶした白いボールを使った。その石灰が、こびりつき、左手がカサカサだがノックをやめるわけにはいかない。実のところそろそろ終わりにしたいとは思うのだが、打っても打っても、長島はくたばらない。アゴを出さない。もちろん、疲れ切ってはいる。ノックのはじめごろに比べ動きはめっきり鈍っている。だが、彼の精神力はいささかの衰えも見せず、一球一球、執拗なまでにボールにくらいついてくるのだ。捕球のさいの第一歩のダッシュが人より早い天性の持ち味−−人はこれを“動物的カン”と称するが、まさにダッシュの瞬間の長島は飢えた動物そのもので、「アホ!そんな球がとれんのか」と叱れば、「クソッ。もういっちょ!」。三塁から本塁へ長島の気迫が山彦のように、ハネ返ってくる。この山彦が途絶えるまではノックをやめるわけにはいかないのだ。
こうした練習を人は砂押式スパルタ訓練と呼んだが、私にいわせれば訓練などというナマやさしいものではなく、白いボールを武器にした私と長島の壮絶な戦いだった。ノッカーの私はともかく、少なくとも受ける側の長島は、(あのやろう、殺してやる)ぐらい思っていたに違いない。とにかく殺気をおびていた。その証拠に、グラウンドをとりまいた他の部員たちは異様な空気に圧倒され、いつしか掛け声が消え、静まり返ってしまうのが常だった。
今考えると気違い沙汰と思えるが、時には、グラブを持たせず、素手でノックを受けさせたこともある。痛い目にあわせてやろうとしたわけではない。むしろ逆で、疲れて長島の反応がうすれてきた時、精神を引き締め、緊張感を呼び起こさせるためにやった。だからこの野蛮な“素手練習”で只の一度も怪我をさせたことはなかった。−−』
 |
 |
 |
 |
グラウンドでの練習はこうして終わるが、二人の戦いが終わるわけではない。そのころ砂押監督の自宅は東長崎のグラウンドから2500メートルくらい離れた所にあったが、こんどはその自宅へ呼びつけての個人レッスンだ。砂押は書きついでいる−−
『一足先に家へ戻って待っていると、やがて智徳寮(合宿所)から、“いま合宿所を出ました”とマネジャーの電話連絡が入る。すかさず時計を見る。十分以内に長島がわが家へ駆け込んでくるのだ。十分をオーバーしたときはもう一度やり直しだから、当然長島は2500メートルを全力で走って来なければならない計算である。
息をはずませ“規定時間”内に到着すると次は素振りだ。200回、300回…手のひらが赤くはれ、やがて皮が破れて血がにじみ出す。手袋を渡す。手袋といっても今のような皮製ではなく木綿の軍手。だがそれもすぐ破れてしまい、いつの日からか練習前に軍手を水につけ、ぐしょぐしょにしておいて嵌めるようになった。
これだけ鍛えながらも、栄養と休養には、気をつかった。素振り練習も夜9時には必ず解放して帰すように心がけ、“ほれ、これ持っていけ”と用意した果物などを渡すのが練習終了の合図で、一日の中で長島がはじめてニッコリ笑顔を見せる時だった。合宿所から“今、着きました”と再び電話連絡が入って二人の戦いは、休戦になるのである
私にとっても長島が猛練習に耐え、大きく成長するかどうかは一種の賭けだったが、彼は見事にそれにこたえてくれた。多くの選手が猛練習に悲鳴をあげ合宿所から逃げ出した中で、ただの一度も弱音を吐かず、最後までくらいついてきた体力、気力にはただ敬服のほかはない。最終的に、これは本人の野球に対する人なみはずれた熱意がそのエネルギーだったと思うが、プロ野球を背負うほどの大スターはすべてにおいて、やはり他の選手とは違っていたのだ。
その後の長島についてはご存知のとおり。今や、はるか遠く雲の上の存在になってしまった。が、私にとっては百年に一人出るか出ないかの大選手と会い、その基礎づくりの段階で多少なりとも関わりを持てた幸せで一杯の気持ちである。
今でも何かのおりにふとあの東長崎の猛練習を思い出す。私の人生において二度とない、またやろうと思ってもできない戦いであった。』
ちなみに、素手のキャッチングで怪我はさせなかったと当人はいうが、野球部員によれば、長島はこの練習で右手を突き指し、それをかばって以前のオーバーハンドから、サイド気味の、ダッシュを利したあの投げ方に変わった。現役時代のグラウンドに見せた彼のダイナミックなフィールディングのかげに、つまり血のにじむこうした苦闘が秘められていたのである。
(動物的カン)などと呼ばれ、天才時と持てはやされた彼のプレーも生まれながらのものではなく、「努力する才能」とゲーテの称したそんあ努力でつちかわれたものなのは、ここに強調しておきたい。後楽園でぼくらがしばしば見たあのサード長島の素晴らしい守備に、誰が《トンネルのシゲ》を想像できたろうか。長島茂雄も亦、努力の人なのである」
 |
 |
異様に長い引用紹介となってしまいましたが、この五味康祐が書いた長島と砂押監督の“戦い”こそ、1960年代を体言することになる長島茂雄のすべてだったのではないかと思うわけです。
8号ホームランの新記録を達成した翌月の1957(昭和32)年12月には、契約金1800万円、年棒180万円で巨人と入団契約。
新人として登場した1958(昭和33)年に、いきなり、打率3割5厘、92打点、29本塁打で、打点とホームランの二冠を達成、あわや三冠王という活躍をし、新人王とベストナインに輝いたという事実は、すでに、立教時代に、長島が超プロ並みのレベルに達していたことを物語るものだろうと思います。
同じ五味康祐の本の中で、「ぼくが入団したころ、プロ野球の練習は子供の遊びでしたよ」「多摩川の猛訓練は川上監督がやったように人は言ってますが、長島が率先してやったから出来たと僕は思うんです。それと王とネ」という巨人の鈴木ランニングコーチの言葉も紹介されています。
五味康祐は、「プロ球界に君臨したONは、努力の所産だったのである。努力させたのは一は中華の民族の誇りであり、他は倦まず黙々と田を耕す日本の農家の習俗が育てたものではなかったか」と指摘しています。
「60年代通信トップページへ 「60年代のイベント」のINDEXページへ
このページをご覧になって、甦ってきた記憶や確かめたい事実、ご意見・ご感想など、ぜひ、「60年代通信」掲示板にお書き込みください
「60年代通信」掲示板=http://www64.tcup.com/6405/kiyomi60.html
お便りもお待ちしています
メールはこちらへ:kiyomi60@bb.mbn.or.jp
(C)1998 60年代通信