|
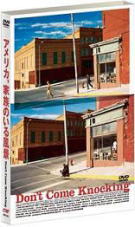 84年カンヌ国際映画祭のグランプリに輝いたロードムービーの傑作『パリ、テキサス』を生んだ、監督のヴィム・ベンダースと脚本のサム・シェパードが、20年の時を経て再びコンビを組んで話題となった『アメリカ、家族のいる風景』を観る。原題は「ノックしに来ないで」と邦題とまったく違うんだけど、見終わった後はなるほどと思わせるタイトルです。なにより本作を撮り終えてアメリカからドイツへと帰っていったベンダースの、アメリカへのノスタルジーと愛がいっぱい詰まった作品になっていた。 84年カンヌ国際映画祭のグランプリに輝いたロードムービーの傑作『パリ、テキサス』を生んだ、監督のヴィム・ベンダースと脚本のサム・シェパードが、20年の時を経て再びコンビを組んで話題となった『アメリカ、家族のいる風景』を観る。原題は「ノックしに来ないで」と邦題とまったく違うんだけど、見終わった後はなるほどと思わせるタイトルです。なにより本作を撮り終えてアメリカからドイツへと帰っていったベンダースの、アメリカへのノスタルジーと愛がいっぱい詰まった作品になっていた。
かつては西部劇のスター俳優だったハワード(サム・シェパード)も、今ではすっかり落ちぶれてしまい、何もかもがいやになり突然撮影現場から逃げ出してしまう。一人身で転々と暮らすハワードにとって、唯一逃げ込める場所はネバダ州に住む母親のところだけだった。30年ぶりに会う母親は、変わらないやさしさでハワードを迎えるが、ハワードは言いようのない不安を拭えずにいた。そんな時、母親がハワードに「家族の写真は?」と問いかける。20年以上も前に、ハワードの子供を身ごもったという女性から電話があったいうのだ。驚いたハワードは、当時の記憶をたどり、モンタナ州のビュートという町へと向かった。
広大な大地と澄み渡る青空、全編に降り注ぐ柔らかな光。さびれているがどこか懐かしい時代を感じさせる町。ヴェンダースの眼差しのように、静かに映し出されるシーンの数々がどれも美しい。ハワードをはじめこの作品で描かれる登場人物たちから、観るものの心の奥に潜む、誰もが抱える孤独と、失ったものへの後悔を垣間見せられる。しかし本作はそんな孤独や後悔に苦しむ人たちの未来を、美しい映像とともにあくまでも明るく、そして優しく映し出していく。やがてそれぞれが手繰っていった絆の先に見えた光は、家族の意味を改めて考えさせられる。またそれはヴェンダースから長く暮らしたアメリカへの、家族という一番近くにある愛への原点回帰のメッセージのようにも感じられた。ラストで迎える爽やかな風と喜びは、観終わった後に、自らを繋いでいる絆をたまらなく愛しくさせる。なぜ西部劇の俳優だったのかとか、ちょっと楽観的過ぎじゃないかみたいなとこもあるが、このあったかい感じ・・・んん〜好きだなあ。T・ボーン・バーネットの音楽も素敵でした。
『パリ、テキサス」も含め本作で、サム・シェパードの劇作家としての顔を、恥ずかしながら調べてみて始めて知ったんだけど、そんな驚きより、冒頭でアップで映ったしわだらけの顔に驚いた。いや〜『ライト・スタッフ』のチャック・イェーガーもずいぶん年取っちゃいましたねえ。でもかなり情けない役だったけど、やっぱ渋いです^^。ただ、吹き替えで聞く情けない声は、声優さんには悪いが最低でしたね。観るときは絶対に字幕で観てほしい。サム・シェパードと実生活でもパートナーのジェシカ・ラングや、みょ〜な存在感を見せたティム・ロスなどの実力派もさることながら、二人の若手サラ・ポーリーとガブリエル・マンに大注目だった。どちらもたぶん初めてみる俳優だけど、難しい役どころを見事に演じてます。
最後に、ああ〜この作品も劇場で見たかったよ〜
|